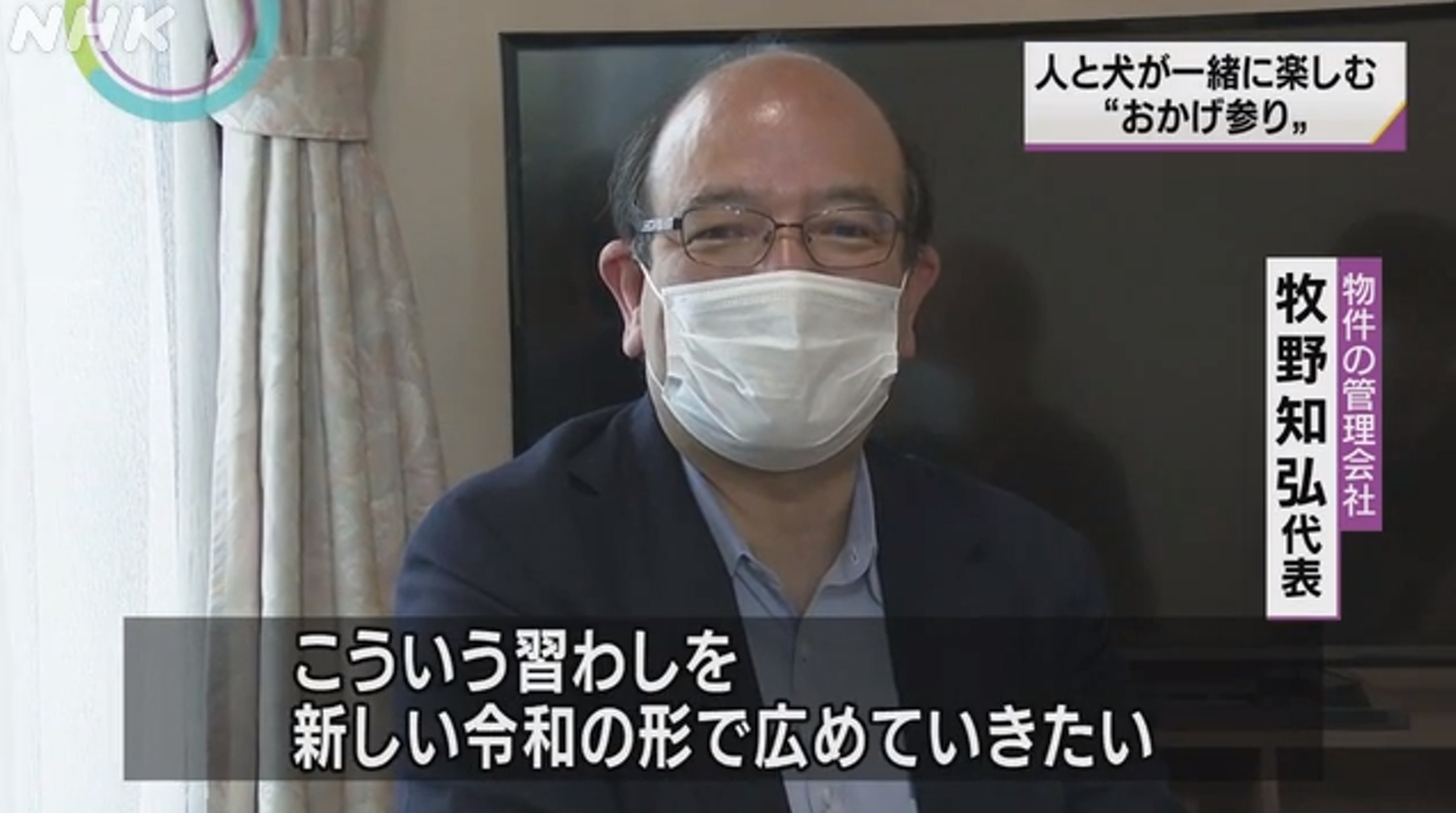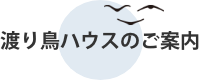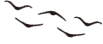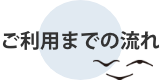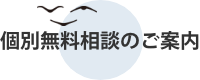フリーランスで実践するリモートワークと、年の瀬迫る京都での暮らし
フリーランスとして活動しているOと申します。この20年間に起業や事業再生に携わってきましたが、50歳を機にフリーとなり企業の顧問や社外役員として活動する傍ら都内の大学院で非常勤講師を兼任するなど柔軟な働き方をしています。育ちは大阪ですが、社会人になってから関西を離れての生活が長くなりまして、京都に滞在するのは云十年ぶりでした。2020年12月に訪れた約1週間の「京都・東山 渡り鳥ハウス」での暮らしとリモートワークの模様をお伝えします。

京都・東山 渡り鳥ハウスに行ってみて
現在、住む横浜から新幹線で約2時間。京都駅に降り立つと、事前にもらっていた渡り鳥ハウスの入居ファイルを参考に、駅から市バス(本数多く便利)に15分ほど乗り、五条坂で降車します。清水寺方面に進み、「茶わん坂」を2~3分ほど上がったところを右折するとハウスに到着します。新幹線を降りてからだと30分ほどです。到着後はハウスの使い方を理解したり、生活基盤を整えたりすることでその日が終わりました。冷蔵庫があるので、数日分の食料と飲み物を買いそろえました。一人旅なので、平常時であれば外食中心でよいのですが、昨今の社会情勢に鑑み、店舗の営業時間の短縮が予想されたためです。また、今回は街の様子を知るために、レンタカーを使わず、徒歩または公共交通機関を利用して移動するつもりでした。滞在中は、毎日10キロ歩くことを目標にしました。なんなら、初乗り1,200mまで460円で利用できるタクシーも使えます。
ハウスでは毎朝4時50分になると鐘の音が聞こえます。お寺の活動開始の合図でしょうか。観光の街、京都の朝は早いのです。翌日は日曜日でしたが、この鐘の音とともに私も起床し活動を始めました。外は真っ暗で寒いです。都会にはない静けさの中、買い置きの食料で朝食を済ませ寺社巡りにでかけました。清水寺から高台寺、八坂神社まで、ざっと歩いて回るとお昼になります。いったんハウスに戻り、午後は翌週のための書類仕事を済ませます。この日、高台寺の夜のライトアップ期間の最終日であることを知り、日が落ちてから再訪することにしました。ライトアップというと、嵐山の渡月橋や嵯峨野の竹林のことは知っていましたが、厳かな仏教寺院と庭園のある高台寺の夜景も見ごたえがありました。しかも、ここの御朱印が昼と夜とで異なるということも教えてもらい、2種類を手に入れ得した気分でした(夜の御朱印は暗闇で光ります)。二年坂から高台寺に向かう途中、小高くなった坂道から眺める夕暮れ時の京都の景色は格別です。

気になるハウスの使い勝手は?
ハウスでは、使いやすいキッチン、湯沸かし機能付きの浴室、洗濯機もあり、日常とほぼ同じように過ごせます。消耗品はひと揃い用意されています。嗜好品や不足のあるものは自分で補充することになります。使い勝手のわからない戸建てを一人利用するため、当初は戸惑うこともありました。
しかし、困りごとを解決するのも旅の楽しみともいえます。今はスマホで容易に調べることもできるので、途方に暮れることは少ないです。何より、いざとなればwataridoriのサポートもあるので安心です。エアコンはありますが、今年一番の寒波が到来したことで京都の底冷えは避けられず、また単身だったこともあり寒さが身に沁みました、覚悟はしていましたが・・・。

ハウスから世界とつながるテレワーク
平日はハウスを拠点にテレワーク中心の生活でした。朝と夕に時間のゆとりができるので、東山エリアを散策しました。残念なことに、営業時間の短縮だったり、週末のみの営業だったりする店舗が多かったです。外国人観光客は皆無だったのでテレビ越しに見たような前年までの賑わいはみられませんでしたが、寺社はいつも通りにあいており、静かな雰囲気で落ち着いて拝観することができました。
テレワークにおいては、ハウスのネット環境はまったく問題ありませんでした。PCセットを持参することで足ります。東京をはじめ各地の同僚とのウェブ会議にも参加できます。また、今回の滞在中には、都内の大学院での授業がありリモートで講師も務めました。時節柄、受講者も遠隔参加でした。台湾、香港のほか、アメリカやスイスからの外国人留学生らと、京都に滞在している私がインターネットでつながり2時間ほど講義を行いました。伝えたいことを文字や言葉、ときには動画を使って表現していくことのできる簡便な時代であることを再認識しました。とはいえ、伝えたいことがきちんと学生に伝わっているのかどうか、Face to Faceで育ったアナログ世代の自分としては心配ではありましたが・・・そして、講義が終わるとハウス内にはいつもの静寂が訪れます。翌日、強い寒波の到来で京都はうっすらと積雪し、終日ハウスに缶詰状態となりました。こうして一週間があっという間に過ぎました。
動静が入り混じる非日常な京都でメリハリある生活ができました。エルニーニョの発生、それも晩秋ということで紅葉はあきらめていましたが、幸運にもギリギリで楽しむことができました。

最後まで京都暮らし・食・寺社を満喫
最終日には、大阪の実家にいる両親を招くことにしました。せっかくなので息子(学生)も呼び寄せ、両親と孫との非日常空間における交流の機会をつくりました。コロナ禍で長く外出を制限されてきたので、両親の足腰が弱っているのではないかと心配していましたが、孫の存在が老親のモチベーションとなり、終始、元気に徒歩での寺社巡りを楽しんでいました。この日は、京阪三条で待ち合わせ、伏見の稲荷大社と宇治の平等院へ電車で出かけました。
関西の冬の名物食材といえば松葉ガニです。カニ料理といえば名所はたくさんありますが、一般には大阪・道頓堀のかに道楽が有名です。三条河原町にもその「かに道楽」京都本店があるのです。かにの刺身からはじまり、かにすき、雑炊まで、かに三昧の食事に一同満足でした。この日は予約をしておかないと入れないという混雑ぶりでした。店内はすべて個室でした。

四条河原町では「甘党茶屋 京 梅園」のあんみつ(蜜)などの和菓子にも舌鼓しました。京都に和菓子店はあちこちにありますが、今回の出会いは、茶わん坂の途中にある和菓子屋「菓匠 局屋立春(つぼねやりっしゅん)」の黒糖わらび餅です。店主によると、コロナ期間中も休みなく早朝から菓子を仕込み、営業を継続されているとのことでした。朝出来たてという黒糖わらび餅を試食させていだたき、生あたたかく上品な食感に魅せられました。和菓子はもともと好物なのですが、その美味しさを再発見しました。淹れたてのお茶までごちそうになり、土産品のほか、復路のお供にと持帰用を余分に購入しました。欲しかった最中(もなか)は品切れだったのは残念でした

京都・東山での生活を振り返って
こうして、私の京都・東山の滞在が終わりました。今回はショートステイだったため、観光ではない生活らしさの一部に触れただけでした。またゆっくりと滞在をしたいと思いました。
移動に関しては、市バスと地下鉄の共通一日券(1,000円)で、主に公共交通機関を利用しました。歩くことで、普段は目につかないような細かいところでの発見があったりして、私は気に入っています。年寄りを連れて歩く際にはタクシーも活用しました。複数で横移動する時には便利です。遠出をされるのであれば、レンタカーも良いと思います。ハウスには1台分の駐車スペースもあります。但し、京都市内の道は細いので小型車をお勧めします。
ハウスの利用は、ホテルや旅館とは違い、地元のルールに従って掃除やゴミ捨てを自ら実施することになります(入居ファイルに記載。わからないことはwataridoriに適宜相談)。なお、コンシェルジュやアンバサダーもいるのですが、今回は短期間の滞在だったのでコンタクトをとりませんでした。自分で家を探し、生活をはじめるのは、手続きの時間や費用もかかりますし、何より短期間だけ借りることのできる物件は限られます。家電などインフラのセットアップの必要がなかったのも便利でした。
次に長期滞在するときには、ここで何をしようか?社会的な事業を何かはじめようか、それとも文化的な学び?できれば、その活動を通じて地域の方々と交流できるといいなと思いました。そして、その地域にも必要とされる持続的な活動にしたいですね。