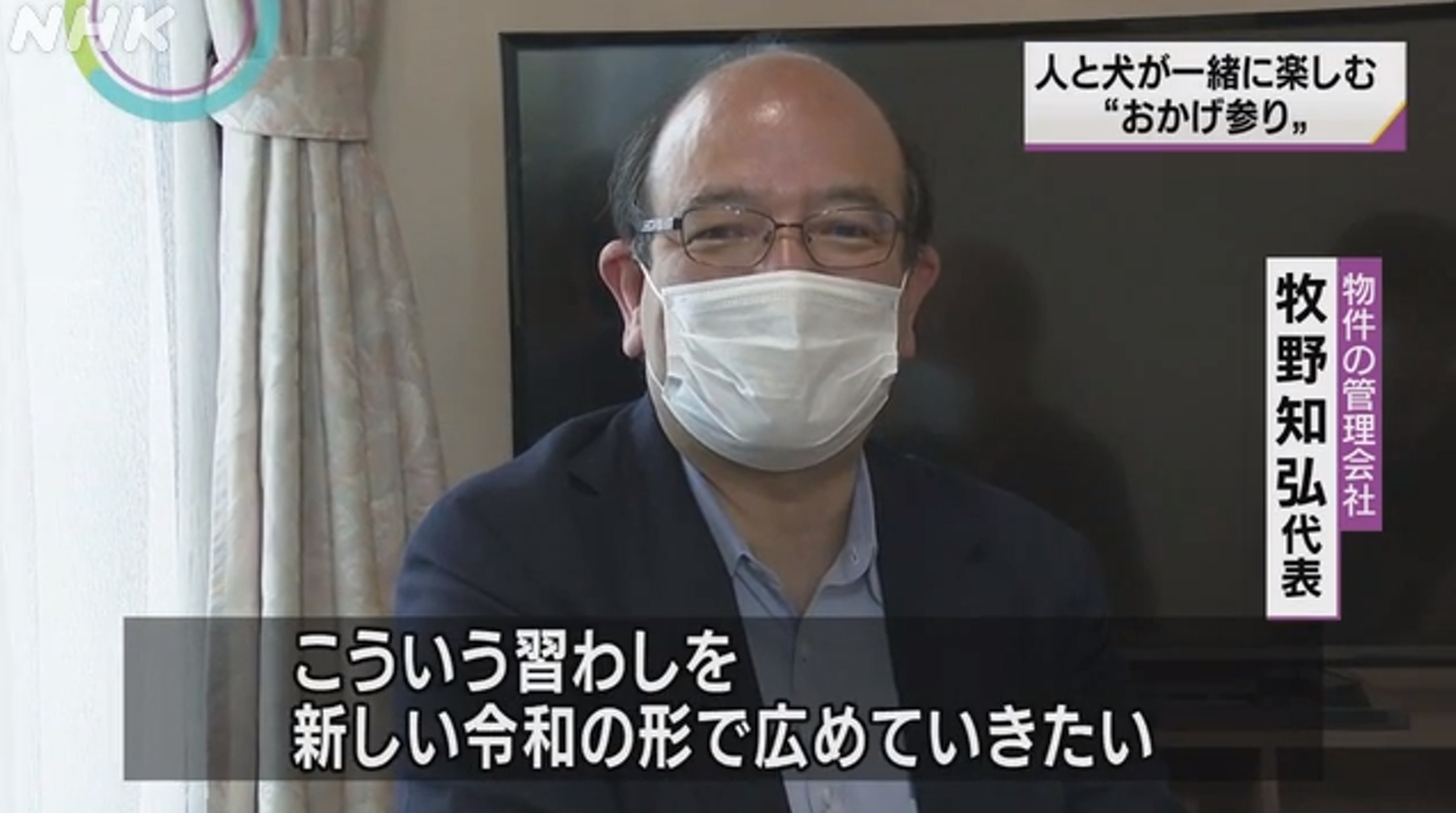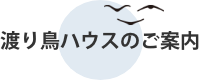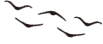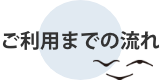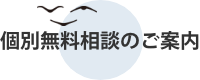wataridoriでは、利用者と地域の人々を繋ぐ地域プラットフォームをご用意
wataridoriは宿泊施設を提供するだけではなく、地域の人々との交流やそこでしか出来ない体験を重視していて、コンシェルジュが地域の人々とのつなぎ役をします。地域の人々との交流や意見交換、プロジェクトへの参画といった、その地域ならではの、都会の暮らしでは得られない経験をwataridoriがサポートしています。
今回は熊本・阿蘇 渡り鳥ハウスをご利用いただいた会員の方に地域交流体験をレポートしていただきました。
地獄温泉で200年以上続く老舗旅館「青風荘」
wataridoriを通してお知り合いになった、合同会社「阿蘇人」の石垣さんに案内いただき、地獄温泉の200年以上続く老舗旅館、青風荘の代表取締役社長をされている河津さんをご紹介いただきました。
2016年に起こった熊本地震の被害を受けたあと、様々な苦労や協力者のサポートを得て、新たに旅館をリニューアルされました。今年本格的に本館がオープンするということです。そこでは「湯治」(温泉地に長期間滞留して特定の疾病の温泉療養を行う行為)ができる施設を建てられ、「湯治」の文化を創造し広めるという新たなミッションを掲げていらっしゃいました。
震災後、ゼロから旅館を建て直すのは相当な苦労だったと思うのですが、「旅館の立て直し作業をやってるとき、200年前の柱が出てきた。その時、自分の先祖がまだ建設技術もなかった当時、さぞかし大変な想いで建てたんだな、と感じたら、今の自分の苦労がちっぽけに思えたんだ」と河津さんはおっしゃっていました。
地獄温泉から、阿蘇へ。阿蘇から日本全国へ。「湯治」の文化を伝え、先祖が大切にされてきた理念を守りながらも、河津さんご自身が今の時代にあった新たなミッションを体現されている姿にとても感動しました。
なかなか私自身普段の生活をしている中では、会えることのなかった方だったんだな、と後になってもその感動が湧き上がってきます。

九州で唯一のコーヒー農園、後藤コーヒーファーム
そのあとは、九州で唯一のコーヒー農園、後藤コーヒーファームへ。農場を経営されている後藤さんにお会いしました。
この農園はビニールハウスで管理され、コーヒーの木は個人のオーナーさんが年会費を支払うことで所有できます。全般的な管理を後藤さんが行うという運営方式。コーヒーの木から始まり、収穫期になるとコーヒーの豆を収穫し乾燥させ、焙煎し、最終的に飲んでいく工程を丁寧に教えてくださいました。普段コーヒー好きの私にとって、このように生産者の方からお話を聞けるのは大変貴重な機会です。
「なぜ阿蘇にコーヒー農園を?」という私の問いに対して、「震災後、阿蘇を元気にしたかった。コーヒーのオーナーさんたち(ほとんどが都心在住の方)が年に何回か、コーヒーの木の状態をみに阿蘇を訪れてきてくれて、そこからそのご家族、ご友人にと広がり、阿蘇にきてリフレッシュしてコーヒーを通して良い体験をしてくれる。そんなきっかけを創りたい」と答えていただきました。
阿蘇は、震災直後はたくさんのボランティアの方が訪れてきてくれたり様々な財政面でのサポートがありましたが、4〜5年経った後の経営を持続可能なものにしていくことが真の課題であるということも教えていただきました。
被災地復興後も、定期的に人が訪れてくれるような長期的な仕組みを作ること、が大切だという観点は、とても重要であることを知りました。

阿蘇での地域体験に触れて
阿蘇のゆっくりと流れる時間、人のおおらかさ、危機を持ち前の明るさや前向きさで乗り越え助け合う文化。阿蘇の人の温かさ、生きる決意、その地域のためになることを個人の方が行動している姿、全てが私にとって大きな刺激となりました。
彼らのように、誰かのため、コミュニティのために行動する姿が、本当に今必要とされていることなのではないのかな。都会にいると感じることができなかった本質的な価値に触れられることができ、とても有意義な滞在でした!